ネットでも、書籍でも、ちまたでも、いろいろ言われているサピックス。そして、ひとり卒業している我が家。いいところも、悪いところも、悪いところも、独自視点で考察します。②回目。
我が家の長女のーさんは、サピックスの宿題をあまりしませんでした。宿題をやっても、やらなくても、周りの反応が同じだからだと思います。
サピックスの仕組み… 復習主義
授業で初見の題材、テキスト、先生の話術で児童に興味を抱かせ、宿題を出し、あとは家庭でよろしく。
サピックスというレールに乗るなら当然やるよね、やるやらないは、児童(および家庭)の責任。というスタイルです。私は、そういうイメージを持っています。
宿題をしない我が子、学年が上がっても振る舞いの変わらない我が子と暮らす中で、塾って、サービス業ですよね、それは無いんじゃない、との想いを募らせた日々でした。
あまりの放置ぶりに、新6年生に上がるときに、他塾への転塾を考え、いくつか説明会にも足を運びました(パパが)。結局本人の転塾をしたくないとの見解により、最後までサピックスにお世話になりました。
直前期の過去問さえも、第一志望1️回、第二志望1回(四教科揃ってないかも…)程度しか提出していないんじゃないかな。そんな状況でもサピックスからは何も言ってこない、そんな放置っぷりでした。
家庭学習
なぜ、こんなことが成り立つのか。サピックスが35年以上続いてきた一因は、専業主婦の優秀ママ達が、御子息のサピ勉を真横で並走してきたからなのではないでしょうか。「母親の狂気」。
ところが共働き世代が爆増し、サピックスのこの量の宿題を果たしてどのくらいの割合の親が見られると言うのだろうか。もちろん、並走しているワーママ、たくさん知っています。本当にすごいと思います。あと、並走パパの登場もあり、成り立っている家庭もあるのかもしれません。我が家は宿題に関しては、完全に脱落組でした。
家庭学習の家庭への投げっぷり、そろそろ限界、ついて行けない家庭が続出するのではないかと思ってしまいます。思ってしまっておりました。次女うーさんが4年生になる前に、サピックス変わってください!と。
「最も強いものが生き残るのではなく、最も変化に敏感なものが生き残る」 by ダーウィン
ところが
受験関連本、サピックスの受験体験記を読み込み、我が家のケースが見当たらなかった私の結論「中学受験は、一人ひとりにとって異なるもの、なぞれる体験なんて無い」と思っていたはずだったのに、迂闊でした。
サピックス生活も人それぞれだと思い知りました。
我が家の次女うーさん、なんと、サピックス宿題に取り組んでから授業に行きます。驚きました。サピックスの宿題をこんなにやる児童がいるんだ…しかも我が子。宿題の範囲を複数回こなすという猛者がいるという話も聞きますが、意味がわかりません。一周するのも大変な量&内容を、何もしないで行く子の存在は近くで見たことがありましたが、親が「その問題はやらなくてもいいんじゃない?」と言っても無視し、指定の宿題範囲をどうにか終わらせようとする子どもがいるとは。うーさん、猛者ではないけど、すごいね。
人それぞれなんですね。
(宿題に誠実に対峙する、こんな日々は、いつか終わってしまうものなのか。もしそうならば、ブログに残せてよかった、この奇跡)
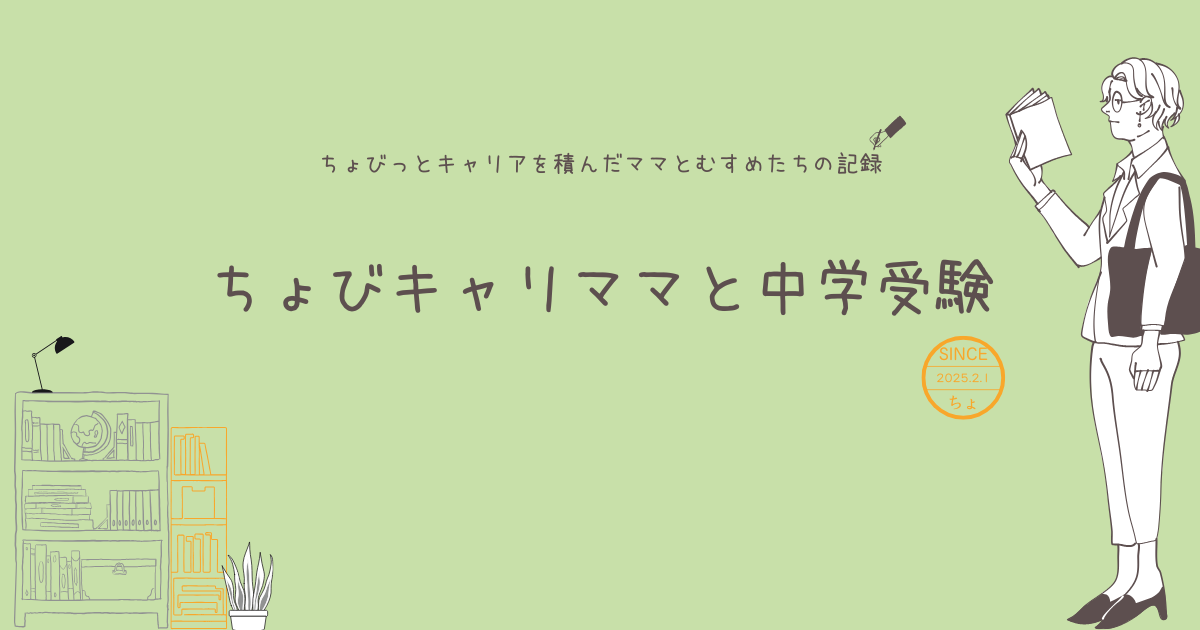


コメント