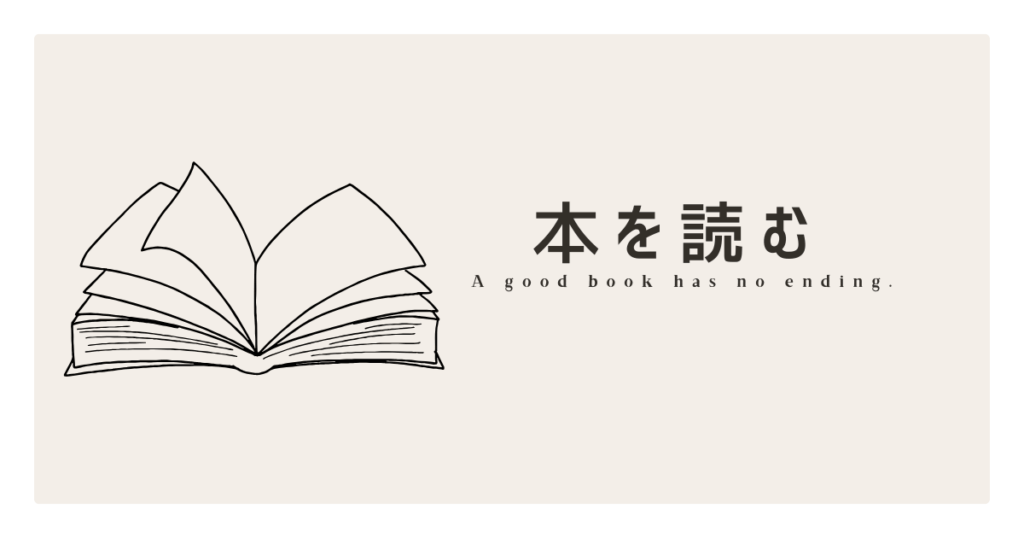
JK、インドで常識ぶっ壊される
熊谷はるか
河出書房新社
夏休みに娘が読んだらいいなと思ったのですが、1ページも読んでくれなかった。私が読みました。
※ネタバレあります。
主人公のお嬢様が、インドでのいろいろなことを記しています。
多感な時期に貴重な経験をしたことを理解し、表現しています。何はともあれ、学生さんがこういうふうに書けるのかな、すごいなと思ってしまう。異文化体験をこんなにしっかりしてしまうと人生変わるだろうなと思います。
著者は、インドに暮らし、使用人を抱える側になる。その良し悪し案件に触れ考えがめぐるわけです。
食事を作ってもらったり、学校に送ってもらうという身分は相応か?という疑問に苛まれ、しかし、作ってくれたり、送ってくれる人の生活費を賄う(役に立っている)意義もある。
子どもが成長の過程で、やってもらっていたことを自分でできるようになる→えらいね、すごいね。という価値観との相違。
仕事のことです。
経験値の違いから、同じ部門に所属していても、人によりできること、できないこと、できる具合など異なります。だから、給料も異なります。
部下にこの仕事をしてくださいという業務命令も、食事を作ってもらうことや、送り迎えしてもらうことと、つまり自分ができることを人にやらせる、と同義か?と巡りました。差別か?格差か?不平等か?
限られる時間で役割を分担する、ことはあっていい。差別ではなく、能力の差による分担だと思います。能力を伸ばして使用側にたどりつける可能性があります。
しかし私も通ってきた、経験浅め側には分かりづらいこともあるでしょうから、業務をオープンにしてやらせてるだけではないことを示しつつ、感謝の気持ちを表現していくといいんでしょうね。
生まれた場所や、生まれた家庭の身分などによって、将来の職業が決まってしまう、という身分制度がキツイなということかと思いました。
娘へ。日本に生まれたので、身分制度は限定的です。やりたいことが見つかるといいね。
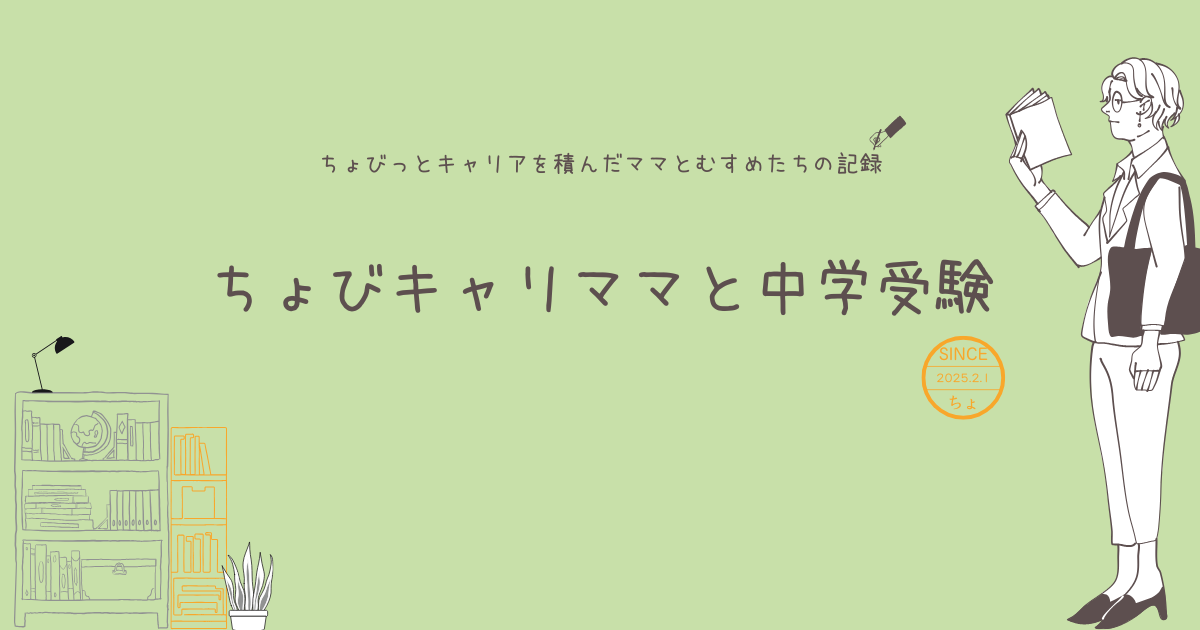

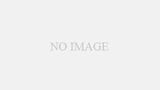
コメント